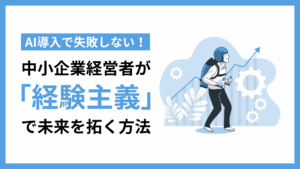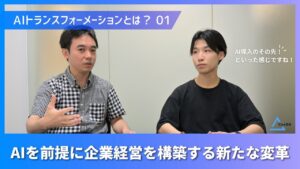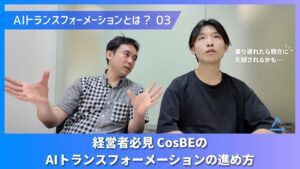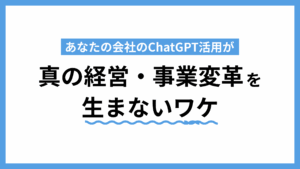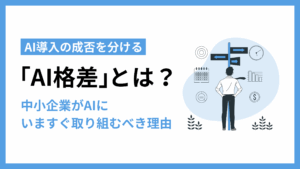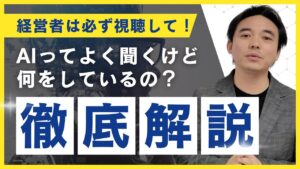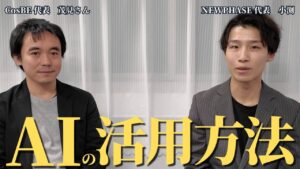【事例解説】AIトランスフォーメーション成功の鍵と陥りがちな落とし穴とは?
製造業から小売まで激変中。「小さく始めて成功する」導入法とは?
「AIツールは導入したけど、事業の根本は何も変わらなかった。」
そんな悩みを抱える経営者に向けて、今回は業界別のAIトランスフォーメーション事例と、日本企業が導入に踏み切れない本当の理由、そして成功する導入アプローチについて、CosBE代表の茂見さんにお話を伺いました。
重要なのは、「自社に合わせた具体的な活用イメージ」を描くこと。そして小規模なプロジェクトから素早く始め、経験を積み重ねていくことで、無理なく事業変革を実現できます。
この記事のインタビュアー
小渕 茉那虎(こぶち・まなと)/株式会社NEW PHASE 代表取締役
動画制作・Web制作を中心に中小企業向けのクリエイティブ支援を展開。都内での経営者交流会も主催しており、経営現場の声に日々触れている。
現在はCosBEの営業顧問として、AIに関心を持つ経営者の声を汲み取り、現場視点での情報発信やインタビューを担当。
製造業を変革するAI駆動型工場の衝撃
製造業のAIトランスフォーメーションでは、「AI駆動型工場」の概念が注目されています。従来の製造業の競争環境を根底から変えるインパクトを秘めており、中国や大企業を中心にすでに取り組みは始まっています。
需要予測から品質管理まで:AIが工場全体を変える
小渕: 製造業についてはどうでしょうか?
茂見さん: 製造業はAIトランスフォーメーションが進んでいる業界の一つで、特に中国を中心にして製造業のAIトランスフォーメーションが進んでいます。AI駆動型工場という概念がありまして、AIを前提に工場でのモノづくりプロセス全体を見直すという取り組みです。
例えば需要予測、どの製品がいつどれくらい必要になるかといったことを予測をさせて、この予測を使いながら材料の手配をしたり、生産工程を最適化したり、これもAIが考えていきます。あるいはそれにもとづいて機械のパラメーターの制御もAIが行います。
在庫削減と品質向上を同時実現する新しいものづくり
小渕: 経営課題としては、在庫の最適化ということでしょうか? 欠品をおこさないようにある程度破棄される事も前提に多く作っていたものを、需要予測に基づいて不要な在庫を極力減らしていくとか、、、
茂見さん: そうですね、「在庫の最適化」もその一つです。他にも「ボトルネック工程を見つけ出し、工程全体を最適化してスループットを最大化する」、「不良が多い工程における品質改善をコンピュータビジョンとAIを組み合わせてリアルタイムフィードバックし不良率を改善する」等もあります。
こうした工場の各課題に対してAIで個別の解決を図るのみならず、これらを連携させる事で、AI駆動型で工場全体のパフォーマンスを向上させる取り組みが行われています。
- 中国主導でAI駆動型工場が急速に普及し、製造業の標準となりつつある
- 需要予測から設備制御まで統合的なAI活用で在庫削減と品質向上を同時実現
- ボトルネック解消と不良品削減により製造業の根本的な経営課題を解決
 茂見氏
茂見氏AI駆動型工場とは、AIが工場運営の中核を担う次世代製造システムです。従来の人主導の生産管理から、AIによる需要予測・設備制御・品質管理が統合的に機能する仕組みへと進化。
これにより在庫削減と品質向上を同時に実現し、人の介在を最小限に抑えた自律的な工場運営が可能になります。
中国の製造業や、日本でも大企業を中心に、AI駆動型工場への取り組みは進んでおり、製造業の競争力向上に大きく貢献しています。
建設業界の残業問題をAIが解決する時代
建設業におけるAIトランスフォーメーションは始まったばかりです。建設業界は、労働力人口の減少による人材不足、現場運営の非効率化、高度化する安全リスクという三つの構造的課題に直面しています。
AIの導入によって、工程管理から営業業務まで、工事の入り口から出口までのプロセス全体を変革する可能性を秘めています。
見積から安全管理まで現場をサポート
小渕: 建設業ではAIの活用はどのように進んでいるんですか?
茂見さん: 建設業もAIによる変革が進んでいる代表的な業界の一つです。現場の作業や管理をAIが補助するケースが増えています。
例えば、AIによる工程管理で工事進捗を最適化したり、画像認識で安全監視を強化したりします。さらに、営業段階での見積や積算もAIが自動作成・チェックし、精度とスピードを高めています。
工事の全工程をAIが自動化
小渕: 監督さんの長時間労働とか、建設業界って本当に厳しい問題がありますもんね。
茂見さん: 例えば工事完了後の報告書作成もAIが補助できます。こうした業務をAIが担うことで、監督者の残業削減や業務負担軽減が実現します。結果として、工事の入り口から出口までの全工程が効率化され、建設業界全体の働き方が大きく変わっていく。このように、建設業においてもAIトランスフォーメーションが進み始めています。
- 営業の見積作成から現場管理、報告書作成まで、工事の全工程をAIが支援
- 人材不足・現場の非効率化・安全リスクといった構造的課題を包括的に解決
- 現場作業と管理業務の両面で効率化を実現し、業界全体の働き方を変革
 茂見氏
茂見氏建設業は、労働力人口の減少による人材不足、現場運営の非効率化、そして高度化する安全リスクという三つの構造的な課題に直面しています。
建設業のAIトランスフォーメーションは、これらの課題を包括的に解決へ導きます。
例えば、AIによる工程管理は工事進捗の最適化を可能にし、画像認識技術は現場の安全監視を高度化します。
さらに、自動見積システムによる営業効率化や、報告書自動生成による事務負担軽減など、現場作業から管理業務まで幅広く支援します。
その結果、監督者の労働環境を改善しつつ工事品質を高め、業界全体の持続的な生産性向上に貢献します。
小売業界の人手不足がAIで劇的改善
小売業やサービス業のAIトランスフォーメーションでは、人とAIの上手な協業がキーとなっています。例えば、AIが店長業務の一部を代替し、人材不足の解消と顧客満足度の向上を同時に実現する取り組みが進んでいます。
AI支援で新米店長でも高度な店舗マネジメント
小渕: 小売やサービスについては何かありますか?
茂見さん: 小売業界でも人材不足は店舗売上に直結する大きな経営課題ですが、店長人材の不足もその一つです。ベテラン店長が減り、新しく任命された店長が店舗運営のあらゆる判断を担う必要がありますが、その負担は非常に大きく、候補人材も希望者も不足しがちです。
AIが店舗のキー人材である店長業務をサポートする事で、店長人材不足を解消し、店舗の業績改善に寄与します。例えば、来店予測データを基に最適な人員配置を自動で提案したり、販売予測から在庫を最適化したりします。さらに、スタッフのシフト希望や業務状況を分析して、店長とスタッフの円滑なコミュニケーションも支援します。
人は接客に集中し働きがいが向上
小渕: だいぶこれって人件費も削減されるから、採用に困ってたとしてもAIで代用できるところがどんどん増えてきて、生産性も上がっていきますよね。
茂見さん: 小売業においては人が不足して売上機会を逃しているという側面も大きいので、人件費の削減を目的とするというよりも、同じ人員で多くのお客様に対応したり、お客様の満足度を高めるところに人が集中したりと、接客の量と質を改善するところが大きいと思います。デスクワーク的な部分をAIに任せて、人は人の価値を高めるところに集中する、という役割分担ですね。
- 店長業務の大部分をAIが代替し深刻な人材不足と育成課題を解決
- 来店予測による最適な人員配置と在庫管理で顧客満足度が向上
- スタッフは接客とマネジメントに専念でき働きがいのある職場環境を
 茂見氏
茂見氏小売・サービス業のAI化は、単なる省人化ではなく「人の価値を最大化する」アプローチです。
来店予測AI(機械学習による顧客行動分析)により最適な人員配置と在庫管理を実現し、スタッフは接客やチームマネジメントなど人間ならではの価値創造に集中できます。
結果として顧客体験の向上と従業員満足度向上を両立し、人材不足という構造的課題を根本から解決する新しい店舗運営モデルが確立されています。
日本企業が陥る「AI導入の壁」とは?
多くの日本企業の経営者はAIの重要性を理解し、個人的にも試用していますが、実際の事業導入には至っていません。その背景には、技術的な問題ではなく、経営戦略と技術実装をつなぐ「翻訳」の課題があります。
理解はできても実行できない現実
小渕: 日本ではAIトランスフォーメーションあまり進んでない企業が多いなっていう印象なんですけど、それはなんでなんでしょうか?
茂見さん: 私がお会いしている経営者の方たちはほぼ全員がAIを自社の経営にどのように活かすべきか、あるいはこのAIパラダイムシフトの時代に自社の経営とどう向き合っていくべきかということはもう皆さん考えていらっしゃって、ほとんどの方はご自身ですでにAIを試されています。
ただ、やっぱそこで止まってしまっていて、どういうことかというと、一般論もわかるし、自分でも使ってみて便利だし、これはすごいと。じゃあ具体的に自社の経営のどこにどんな形でAIを活かしたら価値を生むことができるのか、この自社に合わせた具体的なイメージが湧きません。
コンサルと技術者の間に存在する壁
小渕: 例えば、それこそ事業をAIを使ってどうにかしたいとなった時に、一番相談相手になりやすいのはコンサル領域の事業されてる方かなと思うんですけど、コンサルだけだったらAIトランスフォーメーションまで落とし込むことができないという、そこが乖離としてあるという感じなんですか?
茂見さん: 新しいものに対するアプローチというのは、実際にやってみて課題を見つけて変えていくといった経験主義的なアプローチの方が適しています。この経験主義的なアプローチを取ろうとすると、実際にAI技術を経営の中に組み込んでやってみるということをやらない限りはわからないんですね。
それができるのはコンサル側じゃなくて技術者側だったりするんですね。ところが技術者の方になってベンダーさんとかになっていくと今度は経営戦略の視点がなかなか持てません。
- 経営者の多くはAIの重要性を理解し個人的にも試用済みだが導入に至らない
- 自社特有の課題に対する具体的なAI活用イメージが描けないことが最大の障壁
- 経営戦略と技術実装を統合できる支援パートナーの不足が根本的課題
 茂見氏
茂見氏日本企業のAI導入における最大の課題は「経営戦略と技術実装の分離」です。
従来のコンサルティングは計画主義的アプローチを取りがちですが、AI活用には「実際に作って試す」経験主義的アプローチが効果的です。
しかし経営視点を持つコンサルタントは技術実装ができず、技術に詳しいベンダーは経営戦略が描けないというジレンマが存在します。
この両方を統合できる支援体制の不足が、多くの企業でAI活用が進まない根本的な原因となっています。
成功企業が実践する「小さく始める」手法
AIトランスフォーメーションを成功させるには、完璧な計画を立てるよりも、最小限の機能(MVP)から始めて実際の運用を通じて改善を重ねるアプローチが効果的です。
MVP開発で課題を細分化
小渕: どういう解決策があるんでしょうかね?
茂見さん: 小さく始めてその経験を元に次のプロジェクトに膨らませます。これを繰り返すっていうのが一番です。初動早く試してみてそこで見つけた課題感とかいいところをどんどんブラッシュアップしていきます。その最初に何をするかということを経営者の視点で非常に重要と思える経営課題から目的を決めることです。
小渕: とってもイメージ付きやすいですね。
茂見さん: MVPと我々呼んでるんですけども、解決したい課題を定める時にこれをとにかく細分化してブレイクダウンして解決可能な最小単位のところの目的を設定するんですね。短い期間でたどり着けるであろう目標設定して、この目標を達成するAI を使った専用のプログラムを開発する。
実際の運用で暗黙知を発見
茂見さん: 実際やってみるとわかるんですけど、ある課題を設定して最小単位に絞り込んだつもりでもやっていくと、課題がまた出てくるんですよ。その「実は難しい」をまた社長さんと一緒に話をしていくと、いやこれ実は現場ではこんな風にしてるんだよみたいなことを社長が言うわけですね。
今まで暗黙知だったものをそれを見ながら社長がおっしゃって、あるいは現場の方がそれを言って。だったらそれをAIはこんな風に実現できますよねっていうことで、そこに解決のヒントがあって、それをまた解決して絞り込んでまた次のものを作る。
- 経営課題を最小単位まで分解しMVPとして短期間で実装・検証する
- 実際の運用を通じて企業の暗黙知が可視化され真のニーズが明確になる
- 小さな成功体験を積み重ねることで大きなトランスフォーメーションを実現
 茂見氏
茂見氏MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)は、最小限の機能で実際の課題解決を試すアプローチです。
AI開発では特に効果的で、完璧なシステムを目指すのではなく「動くもの」を素早く作り、実運用から得られる知見をもとに改善を重ねます。
このプロセスで企業の暗黙知(言語化されていないノウハウ)が可視化され、真に必要な機能が明確になります。
結果として予算を抑えながら実用性の高いAIシステムを構築でき、成功確率が大幅に向上します。
経営者が動けない2つの理由と突破法
多くの経営者がAI導入に踏み切れない理由は、技術的な問題ではなく、リソース配分と社内調整の課題にあります。しかし適切なアプローチにより、これらの障壁は克服可能です。
リソース不足と社内調整が主な障壁
小渕: 実際にその社長が行動できない理由って何かあったりするんですかね?
茂見さん: いくつかパターンがあるかなと思います。一つは純粋にそこにリソースが割けません。予算であったり人員であったりご自身の時間であったりです。これが優先順位の問題なんですね。
二つ目が、例えば社内に情報システム部がいらっしゃると。情報システム部の責任者の方がDXやAIトランスフォーメーションというミッションを持って一生懸命動いていらっしゃいます。やっぱりその方の動きをちゃんと高めてあげなきゃいけません。
課題解決を目的化すれば社内が動く
小渕: この社員がやっぱ使いたくないってなったら話がもう途中で終わってしまうと思うんですけど、対策とかってあるんでしょうかね?
茂見さん: 使いたくないって言われることあんまりないんですよ、実は。ポイントは開発を目的するんじゃなくて課題解決を目的にすることですね。課題解決にフォーカスするとそのプロセスで使う技術とか開発っていうのは途中で変わってもいいんです。課題解決にコミットできるかどうかというのが一つポイントです。
- 経営リソースの優先順位と既存システム部門への配慮が主な行動阻害要因
- 開発ではなく課題解決を目的とすることで社内の理解と協力を獲得
- 短期間での具体的成果により全社的な納得感と推進力を創出
 茂見氏
茂見氏経営者がAI導入に踏み切れない要因は主に2つあります。
第一に経営リソース(予算・人員・時間)の優先順位付けの問題、第二に既存の情報システム部門や現場スタッフとの調整です。解決策は「開発」ではなく「課題解決」を目標に設定することです。
具体的な成果が見えれば社内の理解と協力を得やすくなり、技術手段は柔軟に変更可能になります。
重要なのは短期間で目に見える成果を出し、全社的な納得感を醸成することです。
AI革命を勝ち抜く経営者の決断力
AI技術による変革は、産業革命やインターネット革命と同等の社会変化をもたらしています。茂見さんが指摘するように、「AI革命」の時代において、世の中の当たり前が根本から変わりつつあります。
この歴史的転換点において、経営者には重要な選択が迫られています。早期に取り組む企業は競争優位を獲得し、新たな市場を創造する機会を手にします。一方で、様子見を続ける企業は、気づいた時には追いつけない差をつけられている可能性があります。
重要なのは完璧を待つことではなく、「小さく始める勇気」です。製造業ではAI駆動型工場が生産性を革新し、建設業では働き方改革を実現し、小売業では人材不足を解消しながら顧客満足度を向上させています。これらはすべて、経営者が決断し、行動を起こした結果です。
AI技術は手段であり、最終ゴールは企業が目指すべき成長の姿です。今の時代にAI技術を自社の中に組み込みながら将来を描き、実現していく。これこそが、次の時代を牽引するリーダーに求められる姿勢です。
導入の流れと成功事例を詳しく解説
今回は、AIトランスフォーメーションにおける業界別の変革事例と、日本企業が抱える導入課題について茂見さんに伺いました。
次回は、茂見さんが実際に関わった具体的な導入事例をご紹介いただきながら、「実際の導入フローはどう進むのか」「導入時の注意点は何か」「どんな規模の企業から始められるのか」といった、より実践的な内容をお届けする予定です。AI導入を検討されている経営者の方は、ぜひ次回もご覧ください。
私たちCosBEでは、こうした最初の一歩を後押しする「速AIラボ」を通じて、AI導入の検討から実装・改善まで一貫してご支援しています。興味のある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
\AIで業務効率化を実現しませんか?/