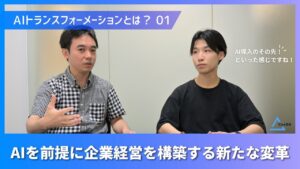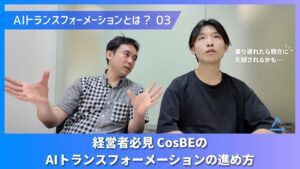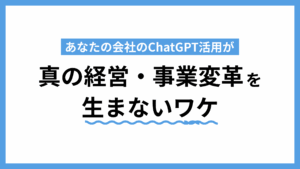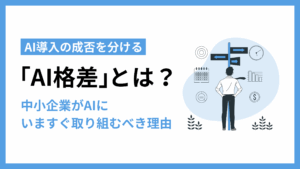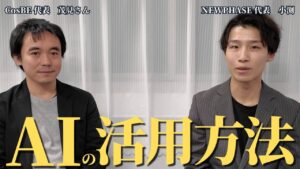【CosBEの茂見が語る】AIトランスフォーメーション|経営者が知っておくべきAIパラダイムシフト時代における基本的な考え方とは?
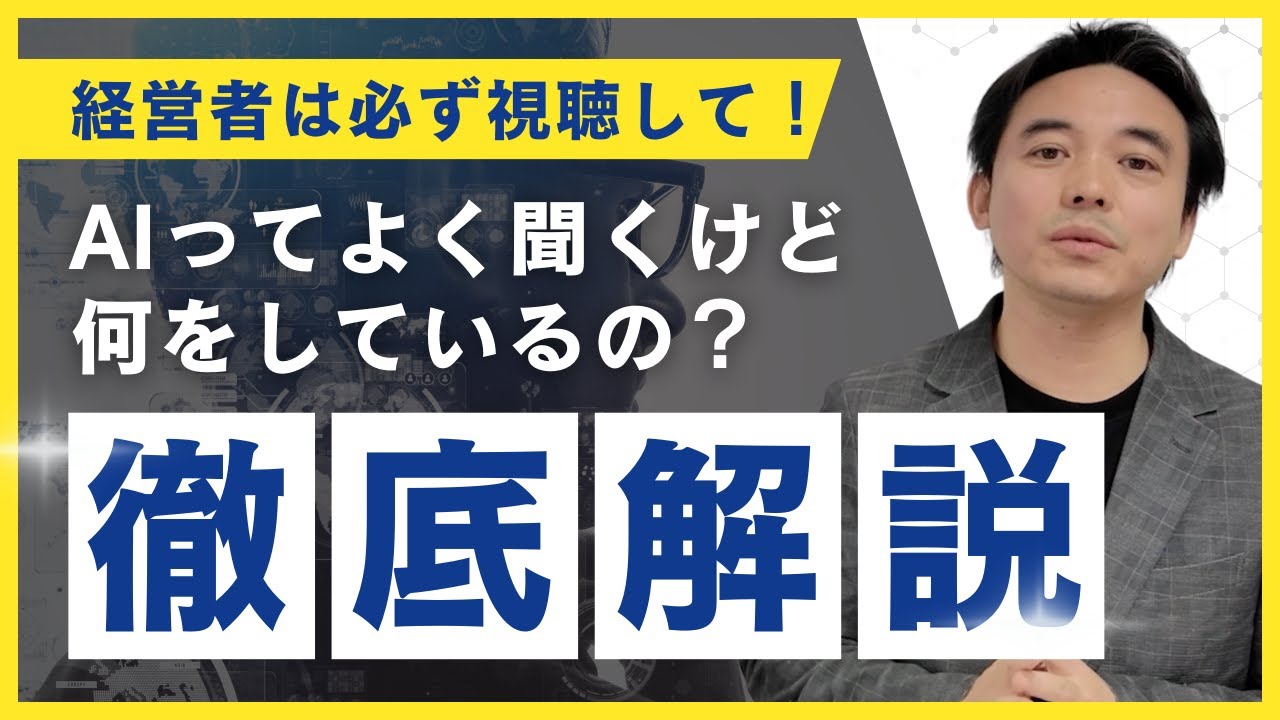
CosBE流・AI導入の基本と実践
AIは今や、中小企業にとっても新たなビジネスチャンスを生み出す現実的な選択肢です。すでに導入を始めた企業では、業務効率の改善だけでなく、事業成長の新たな可能性も見え始めています。
- 「AIに関心はあるけれど、何から始めればいいのか分からない」
- 「ChatGPTは使っているが、それ以上の活用法が見えてこない」
こうした声を、CosBEの営業顧問として日々の経営支援に携わる中で耳にすることが増えてきました。
そこで今回、AI活用の実践知を豊富に持つCosBE代表・茂見憲治郎氏にお話を伺い、AI導入の第一歩として経営者が押さえておくべき基本的な視点を、対話形式で整理しました。
この記事のインタビュアー
小渕 茉那虎(こぶち・まなと)/株式会社NEW PHASE 代表取締役
動画制作・Web制作を中心に中小企業向けのクリエイティブ支援を展開。都内での経営者交流会も主催しており、経営現場の声に日々触れている。
現在はCosBEの営業顧問として、AIに関心を持つ経営者の声を汲み取り、現場視点での情報発信やインタビューを担当。
AIとは何か?私たちの生活をどう変えるのか
近年、ビジネスの現場でも「AIを活用したい」という声が増えてきましたが、実際にはその仕組みや限界について正しく理解されていないケースも少なくありません。私自身も経営者の方と話す中で、「AIってそもそも何なのか?」という根本的な問いを受けることが多くあります。
まずはAIの成り立ちと基本構造について、茂見さんにお話を伺いました。て、AIの基本的な構造から整理していきます。
人が何かを「認識・識別」するプロセスを再現する技術
小渕:まず最初に、そもそも「AI」とは何かというところを教えていただけますか?
茂見氏: はい。AIとは、機械やコンピューターが、人間が行うような「認識」「判断」「処理」といった知的な働きをできるようにする技術の総称です。最近は特に、大量のデータからパターンを見つけ出す「機械学習」という手法がよく使われています。
小渕:たとえば、どんなふうに訓練するのでしょうか?
茂見氏:たとえば、画像認識でいうと「これは犬ですよ」「これは猫ですよ」とラベルを付けた写真をたくさん用意し、それをコンピューターに学習させます。そうすると、新しい写真を見せたときに「これは犬です」「これは猫です」と答えられるようになるんです。
小渕:「人が判断していることを、そのまま真似させる」といったイメージですね。
茂見氏:まさにその通りです。人間の、認識/判断/処理等の知的行動の一部を、コンピューターが再現できるようにする──これがAIの基本的な考え方です。
 茂見氏
茂見氏AIの基本とは、人が行う「見る・聞く・考える」といった行為をデータとモデルで再現する技術だとご理解いただくとよいと思います。
その手法の一つである機械学習では膨大なデータからパターンを学習し、それをもとに新しい情報を認識、判断、処理する仕組みが使われています。
つまり、AIは人間の知的行為を模倣する技術であり、それをどう業務や判断に生かすかが導入のカギです。
- AIは人間の知的活動の一部をコンピューター上で再現・自動化する技術領域の総称
- モデルを構築するための主な手法の一つに機械学習がある(他にはシンボリックAI、強化学習等)
- AIの特性を理解した上でビジネス適用を検討することが重要
【経営者必見】AIでビジネスがどう変わるのか?
「AIは便利なツール」と捉えられがちですが、茂見さんの話を聞いていると、それだけにとどまらない本質的な変化が起きていると感じます。特に印象的なのは、AIの登場が業界の構造や競争環境そのものを変えてしまうという視点。
ここでは、ビジネスの前提がどう変わりつつあるのかを掘り下げていきます。
業界構造を根本から覆す技術
小渕:AIが私たちの生活や働き方に与える影響は大きいと感じていますが、そもそもビジネスの構造にどのような変化をもたらすのでしょうか?
茂見氏:AIによるパラダイムシフトはインターネット革命に匹敵するかもしくはそれ以上の大きな時代の変化点であると言われています。過去に起きた産業の転換点で、私たちがよく教訓にするのがコダック社の例です。
世界最大手のカメラメーカーが、新たな技術潮流への対応を誤り倒産、その一方でデジタルカメラ、スマートフォンと、「新しい価値を作る側」で新たな主役が次々と現れ時代が変化しました。AIパラダイムシフトにより、同じようなことが様々な業界で起こりつつあります。
小渕:確かに、技術が変わると市場の中心プレイヤーも入れ替わる印象です。
茂見氏:まさに今、経営には「既存の延長」ではなく新しい前提を受け入れ、チャンスに変える柔軟さが求められています。AIはただの効率化ツールではなく、これからの価値を再設計するための起点となりえます。だからこそ今動くことが、未来の競争力につながるのです。
 茂見氏
茂見氏AIの登場は、業務の効率化にとどまらず、業界の構造そのものに新たな可能性をもたらしています。
カメラ業界がスマートフォンによって新しい価値を生み出したように、AIに早く取り組んだ企業は、新市場の創出やビジネスモデルの進化といったチャンスを先に掴むことができます。
今こそ経営者が、「AIで自社の可能性をどう広げるか」に目を向けるタイミングです。
- 技術進化は業界構造を根本から変える可能性がある
- AIの導入は「効率化」のためだけでなく、「価値創造」の土台にもなる
- 新しい前提に適応できるかが経営の勝負どころ
【意外と知らない】生成AIとAIの違いとは?
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、「AIの進化」が身近に感じられるようになった方も多いのではないでしょうか。とはいえ、従来のAIと何が違うのか、どう活用すればいいのかは、まだ十分に理解されていない印象です。
生成AIの特徴とその可能性について、茂見さんにうかがいました。
「つくるAI」がもたらす自由度と可能性
小渕:ここ数年で「生成AI」という言葉をよく聞くようになりましたが、そもそも普通のAIと何が違うんでしょうか?
茂見氏:生成AIはAIの一種で、「入力に対して新しいアウトプットをつくる」AIソフトウェアです。文章・画像・音声などをユーザーの指示から生成する能力を持っています。
小渕:ChatGPTとか画像生成AIもそれに含まれるんですね。
茂見氏:そうです。たとえば「このテーマで企画書を作って」と指示すれば、それに合わせた文章が出てきます。重要なのは、生成AIは過去のデータをもとにしつつ、新しいアウトプットをつくるという点です。
小渕:なるほど。既存情報の再整理ではなく、新しいコンテンツが生まれるわけですね。
茂見氏:はい。そして、それがまさに「創造性」や「アイデア出し」の場面で活きてくるのです。
 茂見氏
茂見氏生成AIは膨大なデータ(テキストや画像、音声等)を学習することで、人間のような自然な文章や画像を生成する技術です。
従来のAIが「分類」や「判断」に強かったのに対し、生成AIは「出力する」ことに長けているのが特徴です。
特に企画やデザイン、ライティングなどの分野では業務効率化だけでなく、発想の支援という側面でも大きな力を発揮します。
- 生成AIは「新しいアウトプットをつくる」能力を持ったAI
- 指示に応じて文章・画像・音声などを生成できる
- 創造性の高い業務において、発想支援ツールとしても効果を発揮
AIに学習されていない情報=詰み?実は選択肢は一つじゃない
実際にAIを活用しようとしたときに、多くの企業が直面するのが「社内にある情報をどう活かすか」という課題です。PDFや議事録、マニュアルなどの非構造データを、生成AIはどのように扱えるのか。
この章では、RAGやファインチューニングといった具体的な手法を含め、実務における対応のポイントを整理していきます。
RAGとファインチューニング、2つのアプローチ
小渕:生成AIは汎用的な情報には強い印象がありますが、企業ごとの専門情報を反映させるにはどうしたら良いのでしょう?
茂見氏:そこに関わってくるのが「RAG」と「ファインチューニング」です。RAGとは「Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成)」の略で、AIに対して追加の情報源を検索・参照させながら回答させる方法です。
小渕:なるほど、社内の資料などを読ませるイメージですね。
茂見氏:はい。AI本体のモデルは変えずに、回答時に必要な情報を裏で引っ張ってきて補強するやり方です。
小渕:ではファインチューニングはどう違うのでしょうか?
茂見氏:ファインチューニングは、AIの学習済みモデルに対して、自社独自のデータを追加で学習させて調整する方法です。モデルの中身そのものを更新していく形ですね。
小渕:両者にはどんな使い分けがあるんですか?
茂見氏:ChatGPTなどの生成AIはあくまで「入口」に過ぎません。本格的な業務適用や経営課題の解決には、RAGや独自データ連携など、次のステップを見据えた活用が不可欠です。
 茂見氏
茂見氏RAGは「必要な時に情報を引き出す」検索ベースの方法、ファインチューニングは「AIの脳そのものを育てる」ような方法です。
多くの企業にとっては、まずはChatGPT等のLLMを使ってみて、そこからプロンプトの工夫、RAG、ファインチューニング等と精度と目的の達成度合いを確認しながら段階的にアプローチをしてゆくことでリスクを少なく、スムーズにAI活用を進めやすいでしょう。
下記の記事は実際、私たちが支援したS社の事例になります。
RAGを活用することで社内資料などの独自情報を柔軟に参照しながら、ユーザーの少ない入力から高精度なアウトプットを自動生成できる仕組みを構築しました。
これにより、詳細な要件が固まっていない段階でも、試作品の開発をスムーズに進めることができます。
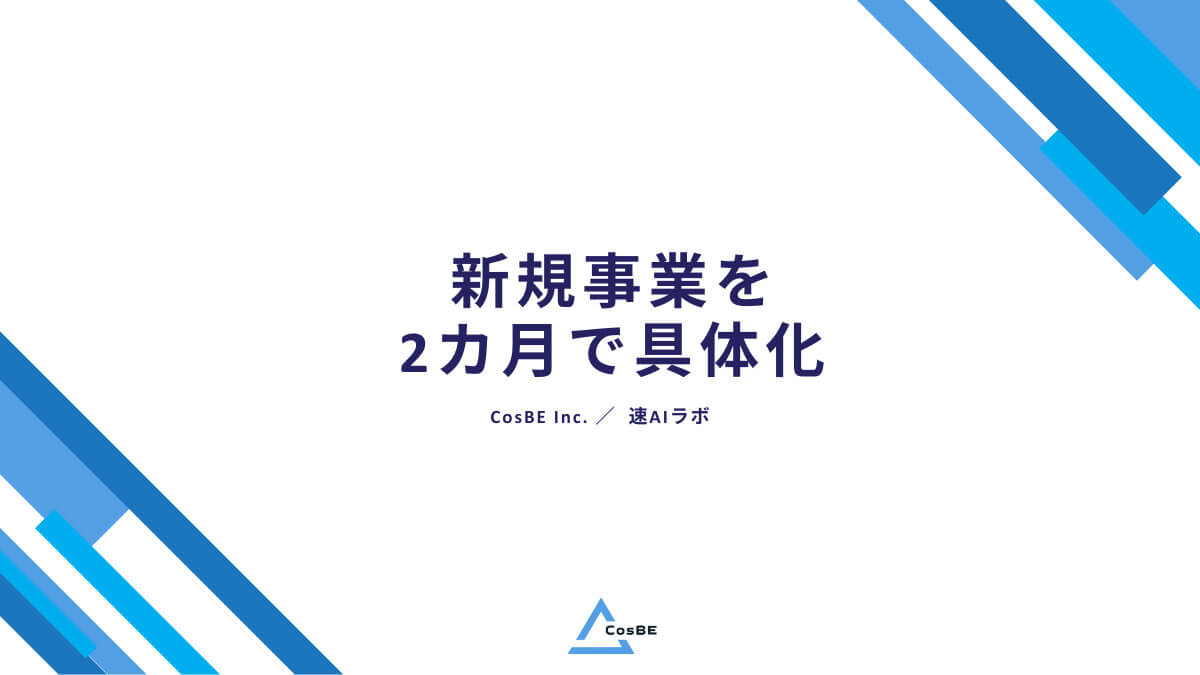
- RAGは社内資料などをAIが参照する仕組み(モデル自体は変えない)
- ファインチューニングはAIに独自データを再学習させる方法(モデルを調整)
- 段階的に取り入れていくステップアップ型の導入が現実的
生成AIより最先端の「AIエージェント」とは?具体的な違いを解説
最近では、「AIエージェント」という新たな概念も登場しています。単に質問に答えるだけでなく、目的に応じて「自ら動くAI」という話を聞いたとき、私自身、これまでのAIとの違いに驚きました。ここではその技術的背景や、具体的な活用シーンについて、茂見さんの見解を紹介します。
「指示待ち」から「目的達成」へ。AIの進化形
小渕:生成AIの次の段階として「AIエージェント」という言葉も出てきていますよね。これはどういった技術なんでしょうか?
茂見氏:AIエージェントは、ユーザーが与えた目標に対して自ら考え、動く仕組みです。たとえば「この資料を読んで、重要なポイントをまとめて会議資料にして」と指示すると、その一連の作業を自動でこなしてくれるようなものです。
小渕:なるほど、単に文章を出すのではなく、最終ゴールに向かってタスクを分解してくれるイメージですね。
茂見氏:まさにそうです。「自律型」と言われますが、AIエージェントは「目的達成型」。連携するツールやプロンプト、実行ステップを統合して判断・行動をしていくのが特徴です。
LLMをベースにしたChatGPT等の生成AIの精度がo3以降で飛躍的に高まったのも、それまで先駆者たちが手動でAIの精度を高めるために実行していた「目的に合わせたタスクの分解」「順次の実行」「結果の評価」「再調整」といったステップを、自律的にできるようになった事が背景にあります。
小渕:実務での活用にはどんな可能性があるんでしょう?
茂見氏:例えば、カスタマーサポートや採用対応、社内研修支援など、定型業務や知識展開の自動化が考えられます。人的リソースに依存していた業務を、AIエージェントに置き換えることで、効率化だけでなく質の標準化も期待できます。
 茂見氏
茂見氏AIエージェントは、「誰かが聞いたことに答えるAI」から進化し、「目的に向かって自ら考えて動くAI」です。
たとえば、人材育成では個人の習熟度に合わせたカリキュラムを提示し、質問対応や評価まで担う「デジタル講師」としての活用も現実味を帯びてきました。
- AIエージェントは「目的達成型」の自律型AI
- 指示を受けて動くのではなく、自ら考えてタスクを実行する
- 業務の標準化・自動化・高度化に大きな可能性を持つ
【AIの進化段階】チャットGPTが使えるのはまだ第2フェーズ!?
AIの導入に興味を持ちながらも、「結局どこから始めればよいか分からない」という声は非常に多いです。私もCosBEの営業顧問として、多くの現場課題に触れる中で、「導入ステップの明確化」が成果の分かれ目だと感じています。
この章では、茂見さんが実践する段階的な進め方をご紹介します。
「目的から逆算する」導入ステップ
小渕:AIを導入するには、具体的にどんなステップを踏んでいけばよいのでしょうか?
茂見氏:実は多くの企業が「AIを使って何かできないか?」というアプローチから始めてしまいます。でも本来は逆で、「経営課題をどう解決したいのか」という目的からスタートすべきなんです。
小渕:確かに、AIありきで考えると本質を見失いがちですよね。
茂見氏:はい。私たちは4つのステージで考えています。
| ステージ | 状態 |
|---|---|
| ステージ1 | AI未導入の状態。 情報収集をしているが、まだ行動には移していない段階 |
| ステージ2 | 個人レベルでの活用。 社員が自分の業務でAIツールを使い始めている状態 |
| ステージ3 | 業務プロセスにAIを組み込んでいる段階。 議事録作成や定型業務の自動化など |
| ステージ4 | ビジネスモデル自体をAI前提に変革している段階。 AIが業務の中核を担う |
小渕:一気に導入するのではなく、段階を踏んで育てていくようなイメージですね。
茂見氏:はい、まずは自社の現在地を上記のステージにあてはめてみていただけたらと思います。すべての企業がステージ4を目指す必要はありませんが、経営目的の達成もしくは経営課題の解決といった観点から、現状がどのステージで、それで充分なのかどうか、現在地を把握することが出発点になります。
そこから、課題を解決可能な単位まで細分化して小さな目標を定め、まず小さなAI導入で目標達成ができているかどうかの確認を行う、そこから範囲を広げてより大きな目標を達成してゆく、といった段階的なアプローチが効果的です。私たちCosBEではこのアプローチを「リーン&アジャイル」として推奨しています。
 茂見氏
茂見氏AI導入は「導入すれば終わり」ではなく、目的に沿って段階的に進めることが成功の鍵です。
まずは自社の現在地を把握した上で目標を定め、その目標を小さな単位に分割して第一歩を素早く確実に踏み出すこと、これが成功の秘訣です。
たとえば私たちが支援した企業では、「いきなり全社導入」ではなく「一部部署でのPoC」から始め、短期間で改善点を見つけることで、確実なスケーリングを実現しました。
- 自社のAIトランスフォーメーションにおける現在地を確認する
- AI導入は「課題から逆算」して段階的に進める
- 検証可能な最小単位の課題を設定し、小さく始める
【戦略から実装までを一気通貫】CosBEが選ばれる理由とは?
多くの企業が「AIを入れること」自体を目的化してしまい、結果として運用に至らずに終わってしまう例も見られます。CosBEではそうした事態を避けるために、あえてスモールスタートから始める設計を採用しているとのこと。
導入初期のフレーム設計から全社展開までの流れを、茂見さんに詳しく伺いました。
成果につながるAI導入には「ステップ設計」が不可欠
小渕:ここまで伺ってきて、AI導入のポイントは「最初から完璧を目指さないこと」だと感じました。CosBEさんでは、どのように支援のステップを設計されているのですか?
茂見氏:おっしゃる通りです。AI導入は「まずスモールに始めて、目的に向かって進化させていく」ことが重要です。私たちは常に、お客様の現状とゴールの間にあるギャップを可視化することから始めます。
小渕:いきなりAI開発に着手するのではなく、まず目的と現状の整理から。
茂見氏:はい。そしてその上で、「AIで解決すべき課題」を段階的に設定していきます。段階ごとにKPIを置きながら、途中で方向修正も可能なフレームを設計するんです。
小渕:実際のプロジェクトでよくあるステップは、どのような形でしょう?
茂見氏:大きく分けて、次の4段階です。
- 課題設定:AIで解決したい経営課題を細分化して特定
- MVP開発:実務で使える最小限のプロトタイプを構築
- 現場運用&改善:現場でのフィードバックをもとに再開発
- 全社展開:成果が出たら他部署や新領域にも展開
茂見氏:この流れを、「技術開発」ではなく「業務プロセスの進化」として設計するのがCosBEの特徴です。技術の話ではなく、経営の選択肢を増やすことを目指しています。
 茂見氏
茂見氏私たちCosBEでは、AI導入を「プロダクト開発」ではなく「事業成長の投資」と捉えています。だからこそ、初期段階では「完璧な設計図」よりも「使いながら学ぶフレーム」を重視します。
課題設定から始まり、MVP、実地運用、そして全社展開へと段階を踏むことで、ムダな開発投資を避けつつ、確実に効果を感じてもらえるよう支援しています。
- 機能で実地検証を行う
- 成果に応じて改善を繰り返し、全社展開へと発展させる
- 技術よりも業務や経営へのインパクトに重きを置く設計が特徴CosBEでは「段階的導入」がAI導入の成功
要因と捉えている - 課題の明確化から始め、MVPにより最小
段階導入こそ、成果につながるAI活用のカギ
AI導入は、最初から全社展開を狙う必要はありません。小さな課題解決から始めて、その中で得た気づきや成果を積み重ねていくことが大切です。たとえば、業務プロセスの中で毎回似た作業が繰り返されている部分があれば、そこから試してみるのが良い入り口になります。
「AI導入=大きな決断」ではなく、「AIをどう活用していくか」という小さな選択の連続なのです。
私たちCosBEでは、こうした最初の一歩を後押しする「速AIラボ」を通じて、AI導入の検討から実装・改善まで一貫してご支援しています。興味のある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
\AIで業務効率化を実現しませんか?/